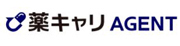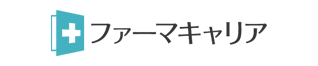※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
この数年、多剤併用、いわゆるポリファーマシー(polypharmacy)の話題が注目を浴び続けています。
ポリファーマシーには、多剤併用によるアドヒアランスの低下、残薬問題だけではなく、多科受診による重複処方や処方カスケードによる有害事象の発生など、様々な問題が含まれています。
こうした問題を解決するために、患者さんのチェックや医師・多職種との連携など、薬剤師の薬学的知識を活かした積極的な介入が期待されています。
このコラムでは、筆者がポリファーマシーの患者さんの処方に対して介入した事例をご紹介しながら、成功した事例だけでなく、うまくいかなかった事例を交えて、高齢者のポリファーマシーの問題について皆さんと一緒に考えていけたら、と思います。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
今回の事例:抗コリン薬による便秘と高用量酸化マグネシウム製剤への介入例
介入のポイント
- 過活動膀胱治療薬のうちムスカリン受容体拮抗薬(抗コリン薬)は、便秘や口内乾燥などの有害事象の原因となる
- 浸透圧下剤である酸化マグネシウムは、腎機能が低下している患者さんでは、高マグネシウム血症のリスクが増大するため注意が必要である
- 処方カスケードが起きている場合、原因となる薬剤に介入することで、複数の薬剤の適正化につながることが期待できる
患者背景
- 80歳後半・女性
- 現病歴:高血圧・陳旧性脳梗塞・心房細動・過活動膀胱(夜間頻尿)・便秘症
介入前の処方
- ランソプラゾールOD錠 15mg 1回1錠(1日1錠)
- リストが入ります
- リストが入ります
ランソプラゾールOD錠 15mg 1回1錠(1日1錠)
アムロジピン錠 5mg 1回1錠(1日1錠)
イグザレルト錠 10mg 1回1錠(1日1錠)
1日1回 朝食後
酸化マグネシウム錠 330mg 1回2錠(1日4錠)
ステーブラ錠0.1mg 1回1錠(1日2錠)
1日2回朝夕食後
介入時の状況と問題点
- 過活動膀胱(夜間頻尿)の訴えがあり、ステーブラ(一般名イミダフェナシン)が処方された後、便秘の悪化がし、酸化マグネシウムが、660mg/日から1,320mg/日に増量された
- 検査値等を確認すると、体重:37kg、血清クレアチニン:0.70mg/dLであり、推定クレアチニンクリアランス(CCr)は約30mL/minで、高度腎機能低下例と考えられた
- 腎機能低下例では高マグネシウム血症発症が懸念され、2015年10月20日には、厚生労働省から、高マグネシウム血症に関する添付文書上の注意喚起を改訂する指示 1)が出されている
医師への情報提供・確認事項
- ステーブラの処方後から便秘が悪化しており、ステーブラの副作用である可能性が考えられる2) ,3)
- CCrが約30mL/minと、高度腎機能障害と考えられるため、酸化マグネシウムは、減量または中止が望ましいと考えられる1)
医師への処方提案
- 過活動膀胱治療薬をステーブラから、β3受容体作動薬であるミラベグロン(商品名ベタニス)への変更を提案した
- ミラベグロンへの変更後、夜間の排尿回数に変化がないことを確認してから、便秘治療薬を酸化マグネシウムからルビプロストン(アミティーザ)への変更を提案した
介入後の処方
- ランソプラゾールOD錠 15mg 1回1錠(1日1錠)
- アムロジピン錠 5mg 1回1錠(1日1錠)
- イグザレルト錠 10mg 1回1錠(1日1錠)
1日1回 朝食後
- アミティーザカプセル 24μg 1回1カプセル(1日2カプセル)
1日2回朝夕食後
- ベタニス錠50mg 1回1錠(1日1錠)
1日1回夕食後
介入後の経過
介護にあたっている家族(娘)から「ステーブラからベタニスに変更後、排尿回数について特に変わりはない。便の硬さがぐっと柔らかくなって、楽になったようだ」「アミティーザに変わってから、便の硬さ、回数もちょうど良さそうだ」との聞き取りができた
介入時の注意点と課題
前回(第3回)に引き続き、今回も、抗コリン作用を持つ薬剤による有害事象へのアプローチを行った症例をご紹介させていただきました。抗コリン作用によって起こされる有害事象により別の薬剤が追加になる、いわゆる処方カスケードの可能性が考えられたケースでもあります。
上述の通り、酸化マグネシウム製剤に対しては、高マグネシウム血症による2015年10月に厚生労働省から添付文書の注意喚起の改訂の指示が出されており、その理由として、
- 高齢者での集積が多く、重篤な転帰をたどる例が多いこと
- 便秘症の患者での集積が多く、腎機能が正常な場合や通常用量以下の使用であっても重篤な転帰をたどる例が報告されていること
- 定期的な血清マグネシウム濃度の測定が行われておらず、意識消失等の重篤な症状があらわれるまで高マグネシウム血症の発症に気づかれない症例の集積が多いこと
の3点があげられています。 特に、腎機能が正常な場合や通常用量以下の使用であっても、重篤な転帰をたどった例がある、という点にも注意が必要です。
今回のケースでは、高齢者かつ高度腎機能障害の患者さんであり、また、血清マグネシウム濃度のモニタリングも行われていなかったため、高マグネシウム血症につながるリスクは十分あったかと思います。
処方カスケードの原因となっていたステーブラの処方を変更し、また、より安全性の高いと考えられるアミティーザへの変更ができたことは良かったかな、と考えられます。
また現在は、リンゼス(リナクロチド)や、グーフィス(エロビキシバット)、モビコール(ポリエチレングリコール)、ラグノス(ラクツロース)など、選択肢も増えており、それぞれの患者さんにあった緩下剤を提案できるようになってきたと思います。
ただし、これらの薬剤は、従来の便秘治療薬に比べ高価なものが多く、今回のケースでも、酸化マグネシウム330mg・4錠=23円/日であるのに対し、アミティーザカプセル24μg・2カプセル=246円(いずれも2019年7月現在)と、約10倍の薬価となってしまいました。
高齢の患者さんの場合、1割負担の方が多いため、高価な薬剤が処方されても、自己負担額が大きく跳ね上がることはあまりありません。しかし、残りの9割は国や自治体の健康保険から支払われており、ポリファーマシーへの介入がかえって医療費増大につながってしまう――そんなケースと考えることもできます。
ポリファーマシーへの介入にあたっては、こうしたコストについても十分検討する必要がある、といえるでしょう。
参考文献
1)独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 酸化マグネシウム(医療用)の「使用上の注意」の改訂について
2)高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015(日本老年医学会)
3)ステーブラ錠 0.1mg 添付文書
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。
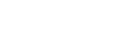

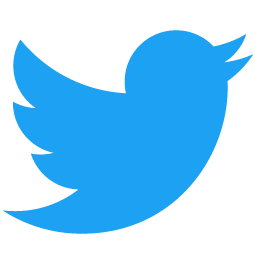 @funa3di
@funa3di