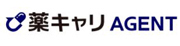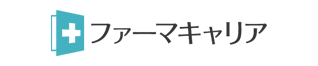※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
こんにちは!栃木県宇都宮市の保険薬局で管理薬剤師を務めている船見です。
現在、調剤をメインの業務とする保険薬局、いわゆる“調剤薬局”の運営は過渡期を迎えています。大手チェーンによる中・小規模薬局のM&A(合併と買収)が進む一方で、毎年の薬価改定、オンライン服薬指導の解禁や薬局の機能の明確化など、薬局を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。
今回は薬局の取り巻く環境の変化から、薬局の将来を考えていきたいと思います。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
大手チェーンによるM&Aの加速
今春に行われた2018年度調剤報酬改定で、大手チェーン店の利益は大きくダウンしたとみられています。
薬事日報の調査によれば、「18年度改定全体に対する経営面での評価としては、“悪い”が約5割、“良い”は1割程度」との評価であったようです。1)特に大手チェーンにおいて調剤基本料1を算定できる薬局が減少し、それに伴い、16年度までの調剤報酬での「基準調剤加算」の代わりに新設された「地域支援体制加算」の算定ができないことが大きな要因の1つとなっています。その一方で、中・小規模チェーン薬局では、大きな影響を受けなかったのではないか、とみられています。
しかし、中・小規模チェーンの経営も盤石ではありません。ペースはかなり緩やかになったものの薬局の店舗数は増加を続けており、薬剤師の需要はまだ伸びています。中・小規模チェーンでは、十分な薬剤師を確保することが難しくなってきています。また、24時間対応や電子お薬手帳などICTへの対応など、薬局の機能や設備への投資などが大きな負担になってきています。
こうした状況から大手チェーンによる中・小規模チェーンのM&Aが加速しているのが現状です。2)
薬局の機能の明確化が進む
一方で、厚生労働省の主導で、薬局を機能別に分類する動きが進んでいます。3) 最低限の機能を持つ薬局、在宅医療に対応する「地域密着型」、抗がん剤など特殊な調剤ができる「高度薬学管理型」の3種類への分類が検討されており、将来的にはこうした薬局の機能によって調剤報酬に差がつくようになるかもしれません。
当たり前の話ですが、全ての薬局に無菌調剤施設や、抗がん剤調製用キャビネットなどの専門性の高い設備は必要はありません。しかし、地域医療に対応する「在宅支援」や「かかりつけ機能」については、「薬局のもとめられる機能とあるべき姿」(2013年)や「患者のための薬局ビジョン」(2015年)において、これらの機能が将来の薬局の「あるべき姿」として、すでに提言されてきています。つまり、開局のための要件を満たすだけの最低限の機能の薬局は「レッドカードに近いイエローカード」を突き付けられている状態、と考えることができそうです。
地域医療への貢献と営利企業としての姿勢
医薬分業が進み、高騰する医療費の中で、調剤薬局だけが設けすぎている、という指摘が以前からありました。そしてその中で、国民皆保険制度という公益性の高い「社会保障制度」と、(特に大手チェーンの)薬局の経営母体である「営利企業」の思想とは、相反するものがある、という議論も、何度も繰り返されてきました。
薬局の経営母体である株式会社は、株主への利益の還元が、もっとも重要な経営施策の命題となります。これまで調剤薬局が雨後の筍のように乱立してきた背景には、保険制度の公益性を“踏み台”にした利益優先の姿勢が具現化されてきたもの、とも言えます。
大手チェーンがM&Aを繰り返し、“数の力”でその利益を確保していくことと、「薬局のあるべき姿」である、地域医療への貢献とを両立させていくことができるのか、その姿勢が今まさに問われようとしている時、と言えるのではないでしょうか。
そしてもしこの数年で、「あるべき姿」になれない薬局には、いよいよ保険制度からの“退場”(レッドカード)が言い渡される時が来てしまうかもしれません。その時に大きなダメージを受けるのは、経営者だけではなく、薬剤師自身が含まれていることは間違いありません。
勤務薬剤師であっても、そうした危機感を持って自身の会社の姿勢を見極め、また自身の業務にあたっていく必要があるのではないでしょうか。
参考記事
1)【薬事日報・「調剤報酬」の影響調査】改定で過半数が経営面を憂慮 (2018/8/20 薬事日報電子版)
2)薬局再編 中小M&Aの波 調剤大手3社が18年度5倍へ 人材不足、集約促す (2018/10/31 日本経済新聞電子版)
3)薬局を機能別に3分類、「在宅医療型」を新設…厚労省提案 (2018/11/8 yomiDr.)
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。
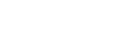

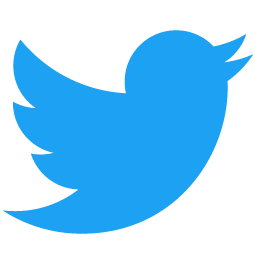 @funa3di
@funa3di