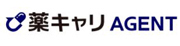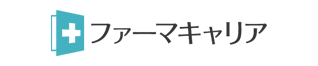※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
こんにちは!栃木県宇都宮市の保険薬局で管理薬剤師を務めている船見です。
1995年1月の阪神・淡路大震災、2011年3月の東日本大震災を教訓に、各自治体では、広域災害時の医療体制や対応マニュアル等が策定、改定されてきました。
阪神・淡路大震災をきっかけに発足した、災害時医療派遣チーム(DMAT)は、医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期(おおむね48時間以内)に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームで、2016年4月の熊本地震や、2018年7月の西日本豪雨災害などでも被災者への災害医療が提供されてきました。
また、東日本大震災をきっかけに、各自治体に、被災地の医療体制を整えるための調整を行う、災害医療コーディネーターが設置されるようになりました。
こうした広域災害時における医療体制の中において、薬剤師もその役割が期待されています。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
災害時に薬剤師に期待されること
東日本大震災の際、被災地には多くの支援物資が届けられました。その中には、医薬品も多くありました。しかし、それらを分別する薬剤師が不足し、必要としている救護施設・医療機関に分配することができなった、という状況が発生した、という話があります。
そうした状況を起こさないよう、現在は各自治体の中で、災害時における薬剤師の役割が明確化されています。
災害時下の薬剤師の役割(東京都の例)
- 被災地内に設置された緊急医療救護所、医療救護所での調剤業務
- 避難所における医薬品(OTC 等)の供給や衛生管理
- 災害薬事センターにおける医療用医薬品等の供給体制の確保
- 巡回医療救護班に帯同しての調剤業務
- 災害拠点病院等の支援
引用元:東京都福祉保健局「災害時における薬剤師班活動マニュアル」
薬剤師に求められる“臨床力”
薬局で勤務する薬剤師にとって、患者さんとの接点といえば、主にカウンター越しの会話であり、より一歩進んだ場合には、在宅訪問時の生活環境やバイタルサインのチェックといったものが主となるでしょう。
しかし、ひとたび大規模災害の渦中に放り込まれたとしたら、そこには、刻一刻と状況の変化する患者さんと対峙する“臨床”の現場と直面することになります。そうした状況下においては、薬剤師ならではの環境衛生への配慮や、限られた薬剤資源の有効活用の提案、医師や看護師と連携しての薬物治療への介入などが必要とされます。
そうした状況下でも、適切な判断を下せるようになるためには、日頃の業務において、ただ漫然と調剤をするだけでなく、医師の処方意図を理解したり、患者さんの臨床データに対してのプロブレムを立てておく、といった姿勢も非常に重要だと思います。
非常時でも落ち着いた行動を取るために
とは言え、万が一、大規模災害が発生した場合には、自分の薬局や医療機関、さらには自宅や従業員宅も合わせて被災してしまうケースも少なくありません。また、公共交通機関の麻痺や道路の寸断などの状況も想定されます。
そうした非常事態に直面した場合、落ち着いて行動することが、正しい判断につながることは言うまでもありませんが、いざ災害が発生してしまってからでは、どうすることもできません。月並みな表現ではありますが「備えあれば憂いなし」、という一言に尽きると思います。
日本薬剤師会では、東日本大震災の教訓をもとに「薬剤師のための災害対策マニュアル」を作成しています。この中には、緊急時の対応だけではなく、平時の準備・防災対策についても記されており、いざという時のために、しっかりと目を通して準備をすすめておく必要があるでしょう。
“救える命”が失われないために
災害が起こらないこと、それが一番望ましいことではありますが、残念ながら、現在の科学技術では、災害を防ぐことどころか、予知することもかなり難しい状況と言わざるを得ません。
過去に起きた数々の大災害から、人間は多くのことを学んできました。そして、そうした災害の際の「救えたはずの命があった」という後悔を繰り返さないために、と、現在の災害時体制や種々のマニュアルが作られています。
少なくとも「災害時に薬剤師に何ができるのか、わからない」、ということではなく、「『救える命』を失わないために、自分に何ができるのか?」を、平時である今から考えておくことが大切ではないでしょうか。
参考資料
東京都福祉保健局「災害時における薬剤師班活動マニュアル」
日本薬剤師会「薬剤師のための災害対策マニュアル」
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。
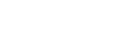

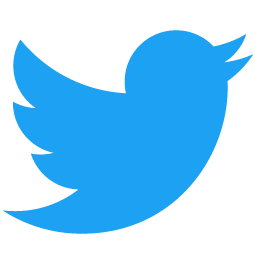 @funa3di
@funa3di