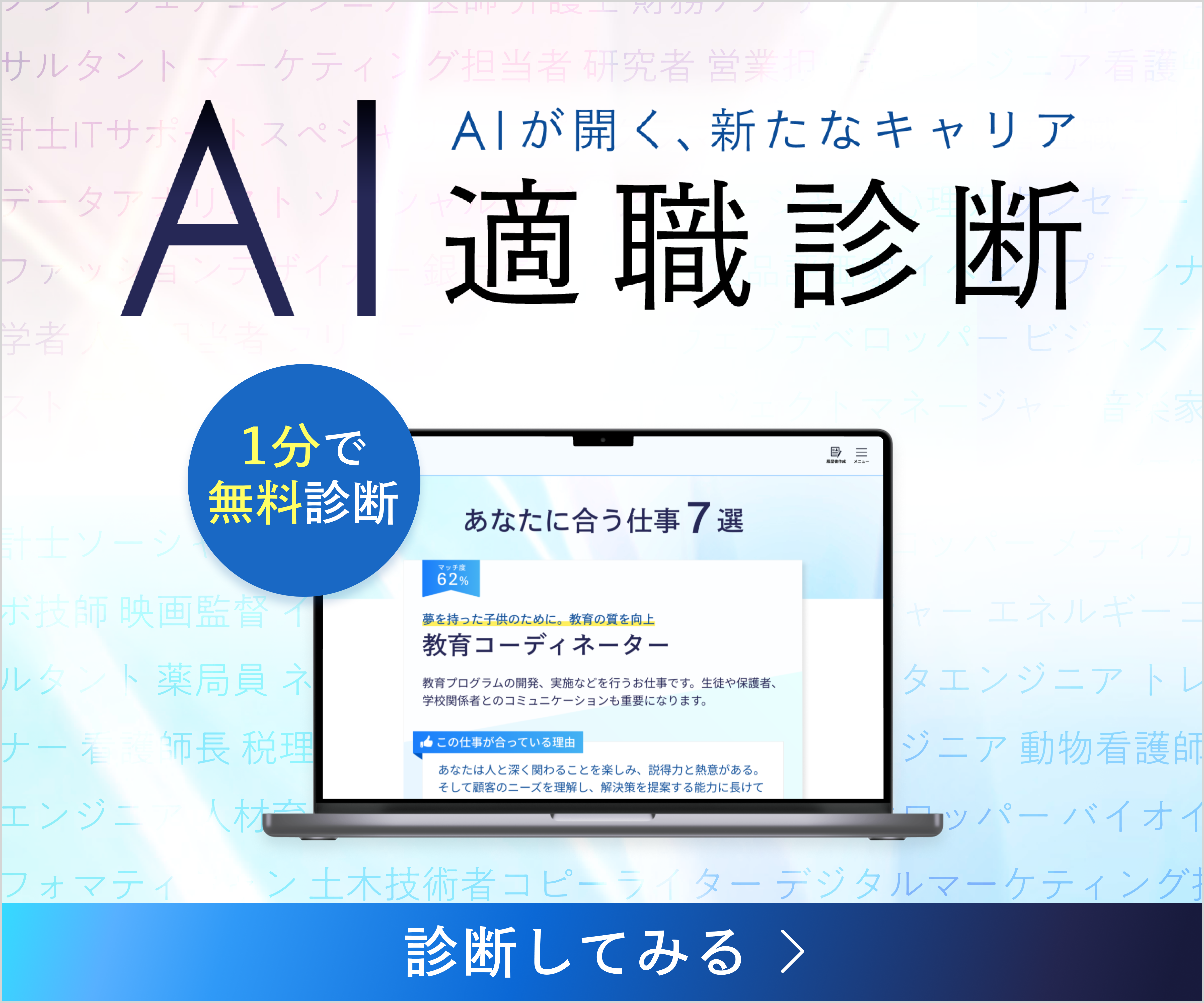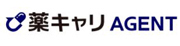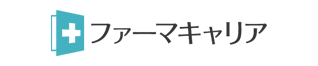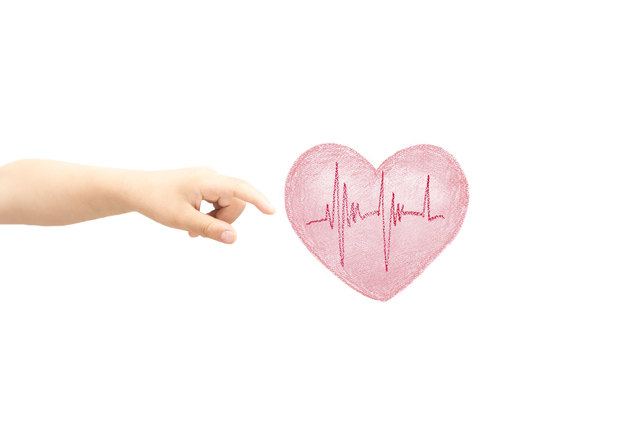
※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
こんにちは!栃木県宇都宮市の保険薬局で管理薬剤師を務めている船見です。
6月13日、中央社会保険医療協議会(中医協)の部会で、薬の値段が効果に見合っているかどうかの基準づくりのために計画していた市民意識調査の中止が決まりました。
先月のコラム(「医・薬・介」三位一体の重要性と促進)でも触れましたが、国民医療費は年間42兆円を超え、医療資源の有効活用は急務となっています。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
「命の値段」はいくらくらい?
1977年・日航機ハイジャック事件の際、当時の福田赳夫首相が発言した「一人の生命は地球より重い」という言葉に代表されるように、日本人の多くが「命を金銭的価値に換算するのは好ましくない」といった感覚を持っているのかもしれません。
一方で、僕たちが生きている“現実世界”では、時に「命」を「対価」で考えざるを得ない場合があります。その一例が「生命保険」です。生命保険の死亡保険金受取額の平均は約283万円です。(参考資料1)
一見少ないようにも感じますが、若い世代では手厚い保障が必要となりますが、高齢になるにつれて必要な保障額が下がるため、平均するとこの程度の金額になるようです。これは「生から死」という変化の代償としての金額と考えることができるでしょう。
逆に、生きるため、つまり「死から遠ざかるため」に必要な金額として1つの目安になるのが「生涯医療費」です。日本人1人が、生まれてから死ぬまで、およそ2,700万円の医療費を必要としており、その約半分(約1,350万円)は70歳を超えた後の人生に充てられている、と推計されています。(参考資料2)
質調整生存年(QALYs)という考え方
さて、ここまでは統計的データを見てきましたが、僕たち薬剤師が実際の業務の中でよく意識するものとしては「薬価」があります。
冒頭の「薬の値段についての市民意識調査」も、この薬価を決めるための1つの基準軸として「寿命を1年間延ばすために、公的医療保険からいくらまでなら払えるか」を盛り込めるかどうかを検討するための調査でした。
この「寿命を1年間延ばす効果」を数値で評価する手法として「QALYs」(クオーリーズ、質調整生存年)という考え方があります。単なる生存期間の延長だけでなく、その生活の質(QOL)の向上・維持を治療効果の指標としよう、というものです。
「1QALY」は「完全に健康な1年間」に相当しますが、既存薬と比較して1QALY延長できる新薬の上乗せ額は、例えばイギリスでは400〜500万円程度以下が目安とされています。
こうした手法や基準を設定することで、いたずらに薬価が高騰することを抑え、費用対効果について医療提供側はもちろん、患者自身も医療費について関心が高くなると考えられます。
日本においても、少子高齢化により増加の一途をたどる医療費の抑制を図るために、今回取り下げられた調査について、(調査方法を見直した上で)議論は避けて通れない課題なのではないでしょうか。
薬剤師として取り組めること
新薬が開発され、その恩恵を多くの患者さん達が享受できることはとても喜ばしいことです。その一方で、新薬開発の成功率は2~3万分の1と言われ、発売前に莫大なコストがかかっています。
そのコストを回収するため、薬価が非常に高く設定された薬が増えてきている、というのが現状です。今回の「市民意識調査の中止」というニュースに接すると、(高い効果が期待できるかもしれないが)とても高価な薬剤が、その価値に見合った適切な使用をされるのか、を評価するための「知識」と「意識」が、薬剤師にも求められる時代になっているのではないか、と感じます。
ただし、そうした評価を行うためのハードルは決して低くありません。患者さんやご家族からすれば、「お金はいくらかかってもいいから、この命を救ってほしい」という思いを持つことは当然ですし、医療者側もそうした思いを受け、それでも「費用対効果に見合いませんから」と一蹴するわけにもいかないのではないでしょうか。
そうした場面にあっても、本人を含めた多くの方が納得できる医療を受けられるよう、日頃から、費用対効果への意識を持ち、患者さんやご家族、医療の提供側、そして健康保険料を納めている国民が共通の認識を醸成できることを意識しながら、薬剤師として業務に取り組んでいくことが大切なのではないでしょうか。
ミライトーチMediaとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。



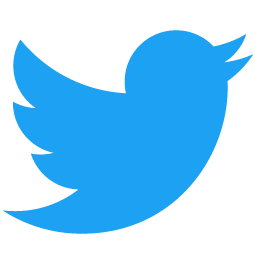 @funa3di
@funa3di