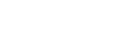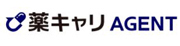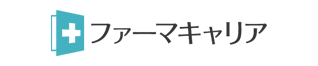※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
各地で猛暑日が続いています。暑さが続くとなかなか仕事にも手がつかなくなりがちですが、営業で毎日外回りをしていた経験のあるけちゃおからすると、室内で仕事ができる薬剤師は恵まれているな、と感じます。
さて、今回は薬局業界の今後に関する記事を3つピックアップして解説させていただきました。薬局で働いている人には、特に共有して欲しい内容となっています。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
処方箋なしで医薬品を不正販売 ドラッグストア大手2社
ニュース概要
ドラッグストア大手のツルハ、ウエルシアの店舗が、処方せんのない患者に不正に医薬品を販売していたことが分かりました。
医療用医薬品の不正販売は、医薬品医療機器法で禁止されています。
ツルハドラッグ小樽店では、門前のクリニックが休診の日に、診察が受けられない患者のために定期薬を販売していたとしています。
同店では、「患者にやましいことですと伝えてはならない」など、不正販売の対応がマニュアル化されていました。
2社とも、今後については「再発防止策を進めていく」としています。
朝日新聞 2019/7/25
コメント
薬剤師としては難しい問題かと思います。心情としては患者さんの要望に応えたい、という気持ちはわかります。ただ結論から言えば勿論不正行為です。
最近では業界全体でこういった不正行為に対して厳しくなってきていますので、今回問題視されました。しかし、以前は業界としてもう少し寛容だったような印象があります。
今回問題となった薬局も、その時代から行っていたことなので、あまり罪悪感を感じることなく続けてしまったではないかと思います。
では、この場合どうするのが正解だったのでしょうか。ツルハの場合、門前の病院が休みの日に、診察が受けられない人のために販売していた、とあります。
しかしこれはおかしな話で、休診日はわかっていますので本来であれば診察日に受診するように誘導するべきです。たまたまその日に薬が切れてしまう、ということなら切れないように日数を調整するなどの対応をすることも必要です。
また、記事からはわかりませんでしたが、病院に無断で行っていたのか、病院も了承の上で行っていたことなのかも気になります。
もし無断で行っていたなら、本来診察を受けるべき患者に対して診察なしで薬だけを渡していることになりますので、病院の利益を奪っていることにもなります。
薬局で働いていると、「薬だけ薬局で販売してもらえないか」といわれることは確かにあります。システム上は患者さんに販売したことがわからないように行うことは可能かもしれませんが、そういったことは初めの段階できっぱりと断るべきです。
実際に断ったとしても患者さんから「どうしてもらえないんだ!」というようなクレームを受けることはまずありません。ルールとして、できないものはできないと明確にして、それを患者さんにも認識してもらうことは大切です。
そうしないと、例えば今回の件で、勝手に薬を渡した結果もし患者さんに健康被害が起きていたら、より大きな問題になっていたことでしょう。
また、ツルハの「店舗が勝手にやっていたこと」という言い分にも違和感があります。確かに販売していたのは店舗の判断ですが、これだけ継続的に不正な販売が続いていたのであれば、本社としても気づけたのではないかと思います。そこに、会社全体としての責任があると思います。
「患者のために」という志で仕事をすることは大切ですが、それが不正販売につながってしまうようでは、結局は患者のためにも、会社のためにもなりません。まずは医療人としての倫理観をしっかり持つことが大切だと感じました。
「ロボット薬剤師」は薬局をどう変えるのか
ニュース概要
大手ドラッグストアや調剤チェーンでは、調剤業務の機械化を進めています。
薬機法の改正により、薬剤師に薬を渡した後のフォローが義務付けられる可能性があることも、機械化を進める一因になっています。
また、4月2日の厚生労働省の通知では、薬剤師ではない人が調剤業務の一部を行っても良いと明文化されました。薬剤師が調剤にかける時間が少なくなり、作業時間も大幅に短縮されます。
ただ、機械化にはそれなりの投資が必要で、薬剤師以外の人員を増やすにもコストがかかるため、小規模薬局では対応できないところもあります。
そんな中、長野県の上田薬剤師会では、薬局同士が連携を取って、個人薬局でも非薬剤師を雇える環境を作り出しています。
個人薬局も生き残りをかけて、早急な取り組みが求められています。
東洋経済オンライン 2019/7/17
コメント
調剤業務の機械化は、ここ数年で急激に進歩しているように感じます。一包化など複雑な調剤もできるようになり、正確性も増していますので、資金力のある薬局は積極的に機械化を進めていくことでしょう。
また、4月に厚生労働省から出された通知では調剤業務の一部を事務員などの薬剤師以外が行うことが認められています。
この二つの事柄から、近い将来、調剤業務に薬剤師がタッチしなくなり、機械や、事務員が調剤するようになっていくでしょう。
機械化が進むと、世間からは「薬剤師の仕事がなくなるので、薬剤師の需要がなくなる。給料も今より低くなる」といったネガティブなイメージばかりもたれます。よくある「今後AIに奪われる仕事」にも薬剤師の名前はよく挙がります。それだけ、世間のイメージでは「薬剤師=調剤」と思われているのです。
しかし、現場で働いている薬剤師からすると、少なくとも今すぐにそのような流れになるとは到底思えません。それは、今後の薬剤師が求められる役割は調剤ではなく、患者との「コミュニケーション」を何よりも重視するものであるからです。
これまでの薬剤師は、薬を正確に調剤する、在庫を管理する、などの「対物業務」がメインの仕事でした。しかし、機械化などによりこれらの業務を薬剤師が行わなくてよくなると、薬剤師の仕事は患者さんとの「対人業務」にシフトしていきます。
服薬指導をして薬を渡したら終わり、ではなく、その後も服用期間中は電話をして状況を確認するなど、継続的な関与が求められています。
また、今後さらに高齢化が進めば、在宅医療の必要性は一層増していきます。在宅医療でも、求められるのは患者さんやその家族とのコミュニケーションです。
調剤業務や在庫管理などを機械に任せることができれば、調剤ミスなどのリスクも減り、それに対するストレスも感じなくなります。
薬剤師としては余裕を持って仕事ができるようになり、他の仕事に時間をかけれるようになります。患者さんと対話する時間が増えれば、薬剤師としてのやりがいにもつながっていくと思います。
このように、機械化が進むということは、薬剤師にとってメリットになることも多いと思います。
ただ、将来的に薬剤師の需要が減っていく可能性はあります。対人業務をしっかりやってもらうために、今までどおりの数の薬剤師が必要と考える薬局もあれば、「調剤業務をしなくていいのだから薬剤師を減らしてコストカットしよう」と考える薬局もあると思います。
そうなれば、当然生き残り競争は激しくなり、これまでなあなあで仕事をしていた人は淘汰されていくでしょう。
コミュニケーションスキルや今後必要とされるスキルを磨いて、いつの時代も薬局から必要とされる人材になれるように努力することが大切です。
長野の上田薬剤師会、クラウドで調剤情報を一元管理
ニュース概要
長野県上田市の上田薬剤師会では、9月からクラウドを活用して地域内の調剤情報を一元管理する実証実験を始めます。
薬局のレセコンを活用して個人を特定し、処方される薬に重複投与や併用禁忌、副作用などのリスクがないかを判断します。
医薬品の適切管理にもつながるため、高齢化で膨らむ医療費の削減に役立つのではと期待されています。
日本経済新聞 2019/7/19
コメント
クラウド上で調剤情報を一元管理するという今回の記事。
現在のところ、患者さんの服薬状況を確認しようと思うとお薬手帳からというケースがほとんどだと思いますが、お薬手帳を持参していなかったり、シールの貼り忘れがあったりということもあるので、それだけで全てを把握することはできません。
しかし、クラウド上で他の薬局の情報まで閲覧できるようになれば、お薬手帳での確認も必要なくなりますし、重複投与などのエラーがあれば教えてくれるので、ミスもかなりの確率で防げるようになるのではと期待されます。
また、今回はこの実験を行っている長野県の上田薬剤師会について少し話をしてみたいと思います。
上記「ロボット薬剤師は薬局をどう変えるのか」の記事でも上田薬剤師会の取り組みが紹介されていますが、他の薬剤師会に比べて薬局同士の連携が取れていて、新しい事業にも積極的に取り組んでいる薬剤師会です。
上田地区といえば、20年以上前の97年には薬剤師会と医師会が衝突したこともあり、問題になりました。しかし、いち早く医薬分業を進め、今では医師会の理解も得ながら様々な事業をすることができるまでに至っています。
また、一つの医療機関からの処方せん集中率を見ると、上田薬剤師会の薬局は33%であるそうです。門前薬局では90%を超えることも多く、全国平均は75%であるのに対しての数字です。
それだけ上田地区の薬局は「かかりつけ薬局」として、地域に根ざした医療が提供できている証拠かと思います。
私が勤めている薬局も含め、薬局の今後はそうあるべきというモデルを示してくれていると思います。いち薬剤師としても学ぶべき姿勢は多いですが、ただ上田地区の薬局がこれだけ成果をあげられているのは、薬剤師会の努力があってこそです。
逆に言うと、薬剤師会が機能していない地域では、個人の薬局がどれだけ頑張っても地域に根ざした薬局にはなれないでしょう。薬剤師会は、地域によってはほとんど活動しておらず、「名ばかり」ところも数多くあります。
まずはその根本から変えていかないといけないと痛感しました。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。今回は、
- 医薬品の不正販売から考える薬剤師のあり方
- 調剤業務の機械化によって薬剤師の業務はどう変わるか
- クラウドを利用した調剤情報の一元管理
の3つについて解説を行いました。
たまたまではありましたが、長野県の上田薬剤師会について触れられた記事が2つあり、薬剤師会として率先して新しいものを取り入れていこうという姿勢に感心しました。
地域の薬局間で連携をとりたいと思っても、会社も異なるのでなかなか足並みをそろえるのは難しいことだと思います。上田地区のような薬剤師会がもっと増えてくれたらと思います。
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。