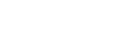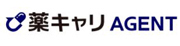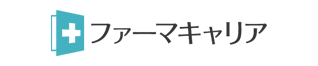※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
目の前で交通事故が起きたら、そしてその人が自分が投薬したばかりの患者さんだったら、あなたはどうしますか?119番通報をして救急隊員や救急救命士が駆けつけるまでの間、薬歴を知っている薬剤師だからこそできる処置があるのではないでしょうか。
「薬局の内外で起こりうる緊急時の対応も僕ら薬剤師ができるようになれば、医療連携が生まれて救急のインフラになる」。そう語るのは、NPO法人薬剤師緊急対応研修機構理事長・山口 勉(やまぐち・つとむ)さんです。
薬剤師のための特定訓練競技会「薬剤師メディカルラリー」を定期的に開催し、コース運営者として活躍しています。薬剤師メディカルラリーをはじめた経緯やそこに至るまでの想いを伺いました。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。

話を伺った人:山口 勉(やまぐち・つとむ)さん
NPO法人薬剤師緊急対応研修機構の理事長。都内の薬局に勤めながら、日本救急医学会認定ICLS(医療従事者のための蘇生トレーニング)のインストラクター資格を取得。薬剤師のための「薬剤師メディカルラリー」を開催するなど、多岐に渡って活動している。
仮想医療現場を超実践型で学べる「薬剤師メディカルラリー」

――山口さんは薬剤師として働きながら、「薬剤師メディカルラリー」のコース運営者としても精力的に活動していらっしゃると伺いました。「薬剤師メディカルラリー」は、どういった取り組みなのでしょうか?
山口さん:はい。「薬剤師メディカルラリー」は、緊急時対応、調剤技術、DI、接遇などの現場を実践的に学べる、“ 薬剤師 ”のための医療技術の競技会です。心肺蘇生術や気道確保の正しいやり方など、災害や大事故などのシナリオ(仮想医療現場)に合わせて救命救急の技能を競います。
――シナリオ?
山口さん:仮想医療現場での「想定」「出来事」などのことを「シナリオ」と言います。たとえば、地震発生から数日後の避難所に支援のため薬剤師チームが入るという設定。一刻を争う場面を想定した現場では、的確な判断・観察・処置が求められます。
――実際に起こりうる、リアルな現場を想定したメディカルラリーによって、現場判断や処置能力も磨かれていくと。
山口さん:はい。倒壊家屋から助け出された人の救護、被災現場でのケガ人措置など、メディカルラリーで実施したシナリオは、2016年に発生した熊本地震でもその経験が活かされたと聞いています。
「薬剤師だからできません」はかっこ悪すぎる

――でも、どうして薬剤師がメディカルラリーに参加する必要があるのでしょうか?メディカルラリーというと、ドクターやナース、消防隊員、救命救急士といった救命医療スタッフが参加するイメージがあるのですが……。
山口さん:AEDの認知度が高まり、デパートや駅の構内で見かける機会が増えはじめた頃、医療者の役割って一体何だろう?、と思うようになりました。自分が買い物中に、突然目の前で女性が心臓発作で倒れてしまったとします。
一刻を争う状況にも関わらず「いや、私は(僕)は薬剤師だから心肺蘇生はできません」って知らん顔するなんてカッコ悪すぎる。
――はい。
山口さん:見て見ぬ振りをするのは、『医療者』として考えたときにどうなのか。倒れている人ひとり助けることができないでは、薬剤師、医療従事者を名乗っている自分としては、「かっこ悪い」のではないかと思いました。
――救急隊員が現場に駆けつける前に心肺蘇生ができていれば、もしかしたら意識が回復するかもしれないし、搬送先の病院でおこなう処置も大きく変わりますね。
山口さん:そうなんです。知人の紹介で、目の前で倒れた心停止の患者さんに対して10分間ケアをするという「※ICLSコース」を受けてみたんです。日本の医療従事者の間で有名なコースで、除細動器(心室頻拍などの不整脈に対し、電気的な刺激を与えること)もパッケージに含まれているんです。
※日本救急医学会による医療従事者のための蘇生トレーニングコース
――蘇生のために必要な専門的な技術や現場でのチーム医療を、みっちり学ぶことができるんですね。ICLSコースには、どんな方々が参加していたんですか?
山口さん:ドクター、ナース、救急救命士だけではなく、歯科医師、臨床検査技師などさまざまな職種の医療関係者が参加していました。そこで一番感激したのは、インストラクターの教え方です。
「上手にできていますね。あとは◯◯をもう少し◯◯すればいいだけなので、もう一度やってみましょうか」って。
高い救命技術を持っている人ばかりの中、知識も技術もなく弱気になっていた自分にとって、インストラクターのその言葉はとても励みになりました。
――自信にもつながりますね。
山口さん:プロフェッショナルな人から褒めてもらえると、承認欲求が満たされるというか、モチベーションが上がって、もっと学びたいって前向きな気持ちになれるんです。インストラクターの手厚い指導のおかげで、コース内容はひと通り学ぶことができました。
なので、今度は人をやる気にさせる教え方を学ぼうと思い、インストラクターになるためのコースを受講してみることにしたんです。そこでの救急隊員との出会いのおかげで、今の自分が在ると言っても過言ではありません。
こんなに頑張ってる人がいるのに、一体自分は何をしているんだ?

▲頭部保持をおこなう様子。
【頭部保持】
外傷による頸椎損傷の疑いがある傷病者に対しておこなう措置。
※頭部や首に損傷や骨折している可能性も高いため、むやみに角度を変えないのが絶対。
山口さん:引き締まった体の救急隊が、めちゃくちゃ頑張っていたんです。救急隊員は、事故や火事など、死と隣り合わせの壮絶な現場で冷静に判断・対処ができるよう、昼夜問わず厳しい訓練を受けています。
その救急隊員たちがこんなにも頑張っているのに、多くの薬剤師は「調剤マシーンになるのは嫌だ」とか「単純作業の繰り返しなら誰でもできる」だとか、不平不満を言ってばかり。
――自分は一体何をやっているんだと。
山口さん:めちゃくちゃかっこ悪いじゃないですか。必死に頑張っている救急隊員の姿を目の当たりにし、「心肺蘇生はできるけど、交通事故にあったケガ人対応はできない」と知らん顔するのも、それも違くないか?と。
「救急隊員のために、薬剤師としてできることは一体何だろう」と考えるようになり、外傷のコースも受講することにしました。
――薬剤師の仕事は多忙だと聞きますが、積極的に色んな研修に参加してたんですね。
山口さん:はい。薬剤師が救急隊員が現場に駆けつける前に患者さんの措置をできるようになれば救命のインフラになり、より質の高い医療連携が生まれるんじゃないか、と思いました。でも、当時私が受けようとしていた「JPTEC(救急救命士などが受講する、プレホスピタル(病院前)での外傷教育プログラム)」は、薬局薬剤師は受講対象外だったんです。

山口さん:地区や病院ごとの研修でお世話になっていた医療従事者とのお酒の席で、「何で薬剤師は受講できないんですか!」って、冗談交じりで散々わめき散らしました。お酒の力を借り酔ったフリをして(笑)。そうしたら、「受けるだけなら良いよ」って言ってくれる方が現れたんです。
嬉しくて、地区の救急隊員たちに「やっと受けられるようになりましたよ」って報告したら、「訓練してあげるからおいでよ」って個別に訓練させてくれたんです。
――すごい!
山口さん:意識の正しい確認の仕方や気道確保の方法など、数日間みっちりと丁寧に教えてくれました。JPTECを受講したり、救急隊員に教わるようになってから知ったのですが、救急隊員が現場に到着してから外傷者に最初におこなう「GUNBA(グンバ)」という問診法があるんです。
-
【GUMBA】
- G(原因)・・・どのように怪我や病気をしたのか聞くことで、受傷機転をその場で病院搬送時に医師の診断に必要な処置や対応を検討できる。
- U(訴え)・・・一番痛む箇所を聞くことで、怪我や疾患を特定しやすくなる。
- M(飯)・・・病院に搬送後に緊急オペになる可能性もあるため、最後に食事をした時間を確認をする。
- B(病歴)・・・飲んでいる薬と病歴。
- A(アレルギー)・・・薬でアレルギーがあればその薬を使わないよう事前に対処ができる。
――外傷者から情報収集できていると、病院に着いてから処置をおこなうまでの時間も短縮できますね。
山口さん:はい。救急隊が来るまでに意識がなくなってる人もいるので、聞き取りが不能ということも十分に起こり得ます。でも、外傷者が薬局の患者であれば少なくとも最後の「B」と「A」は薬剤師は把握していますから。
――確かに!服用している薬やそれまで飲んでいた薬の薬歴、アレルギーなども薬剤師であればわかりますね。
山口さん:血液がサラサラになる薬を飲んでいる人であれば、中和剤を用意しておくことも可能です。救急隊員が現場に駆けつけるまでに、「GUMBA(グンバ)」での問診も済ませて止血も終わっていて、「これが◯◯さんのお薬手帳です」って、薬歴も伝える。
ここまでのフォローアップが完璧にできていたら、医療連携が非常にスームズになるんです。これこそが、薬局がその地区にある理由であり、これからの薬剤師・薬局に求められる存在価値のひとつなのではないかと思っています。
まとめ

取材の最後、山口さんは今後の展望について「薬剤師メディカルラリーへの参加者を増やすこと。そして、心肺蘇生術や外傷者の処置ができる薬剤師を日本全国に増やしていきたい」と語ってくれました。「薬剤師メディカルラリー」の活動を普及させていくことが、山口さんが理想とする薬剤師のあるべき姿なのです。
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。