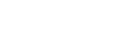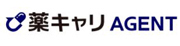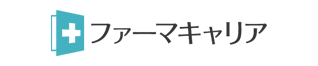※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
こんにちは、けちゃおです。最近は、話題となるのは新型コロナウイルスのことばかりですね。
様々な場面で「自粛」を求められるようになり、普段の生活や経済活動にも大きな影響が出てきていると実感します。そして、それは薬剤師の業界も例外ではありません。
今回は、「自粛」というキーワードから3つの記事をピックアップして、薬局、薬剤師業界にどのような影響が出ているのか、今後どうなっていくのかを考えてみたいと思います。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
初診患者、処方薬も自宅で購入可能に 調剤大手が対応
ニュース概要
4月7日に病院での初診患者へのオンライン診療が解禁されました。
それに伴い、日本調剤などの調剤大手3社は、薬局でも初診患者のオンライン対応ができる態勢を整えています。
今回の措置はあくまで新型コロナに対応するための一時的な措置ではありますが、9月には一定の条件で正式に認められる予定です。
薬局についても、同様の措置が取られる可能性は高いとみられています。
現在のところ、調剤薬局で遠隔対応しているのは調剤大手3社の2500店舗、割合にするとわずか4%にすぎませんが、今後大手に倣う企業が増えてくることも予想されます。
日経新聞 2020/4/8
コメント
以前からこのコーナーでも何度か取り上げてきましたオンライン診療について改めて考えてみます。
これまでは法改正があってもなかなか普及が進まなかったものでしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて一気に普及が加速しそうです。
オンライン診療の最大のメリットは、なんといっても外出しなくても診療が受けられるという点です。特に新型コロナ感染が危惧される今の状況では、感染予防という観点で特に注目されています。
実際、定期で医者に通う必要があるのは、高齢者や糖尿病などの持病がある人が大半です。
しかし、こういった受診の必要性が高い患者であっても、中には感染を恐れて病院に来なくなってしまった人も見受けられます。
その人たちは新型コロナの感染により重症化するリスクがありますので、特にオンライン診療での受診が勧められるところです。
これまでのオンライン診療の対象は、こういった慢性的な疾患で病院にかかる患者のみでした。
しかし、今月7日に初診患者へのオンライン診療も解禁されましたので、より幅広い患者に対して使われることになっていくと思います。しかし、これまで遅々として普及が進まなかったツールが、急に使われるようになるのでしょうか。
ここで、オンライン診療の課題と、どの程度普及していくのかを自分なりに考えてみたいと思います。
オンライン診療普及のために考えられる一つ目の課題は、患者側の受け入れ態勢の問題です。特に高齢者にとっては、ネット知識に乏しく、テレビ電話の利用経験がない人も多くいます。
そのような人たちにとっては、「新しく便利なサービスが始まった」という認識はあっても、「どうせ自分にはわからないから」と考えて始めることをためらってしまうのではないかと思います。
また、その利便性は理解していても、「実際に医師に会って話を聞いてもらいたい」と考えている人も多いと思います。そういったイメージを覆してどれだけ「手軽さ」などをアピールできるか、という点も今後の普及のカギになるかと思います。
二つ目は、病院、薬局側の受け入れの問題です。「オンライン診療」という言葉が大きく取り上げられているため、「どの医療機関でも利用できる」と思われてしまいがちですが、当然すべての病院、薬局がそれに対応しているわけではありません。
特に薬局では今回の記事に書かれているように、対応しているのは大半が大手の薬局です。私が勤めている薬局は、業界ではいわゆる中堅レベルの会社ですが、まだオンライン診療に対応するなどの具体的な話はあがっていません。
もちろん、門前の病院がオンライン診療を始めるかどうかで変わってくるものですが、現在遠隔対応しているのは4%と言われている中で、今後どれだけ対象が広がっていくのか注目したいと思います。
最後は、今回解禁された初診患者に対して想定される問題点です。慢性疾患の場合は、大きな変動がなければ薬も継続で処方することができますので、オンラインで体調変化の有無を確認して処方する、という流れで簡略化が可能です。
しかし、初診の場合はまず医師がどのような症状なのかを確認し、診断しなければなりません。当然、オンラインではテレビ電話を通した情報しか得ることができませんので、場合によってはレントゲンやCTを撮るために結局病院を訪れることになってしまったり、オンラインのみで完結しようとすると誤診が起こるといった可能性も考えられます。
将来的には確実に普及していくオンライン診療ですが、拡大を急ぎすぎてもいけないと思います。
新型コロナ、9割の薬学生が「就活に影響あり」
ニュース概要
新型コロナウイルスの感染拡大により、薬学生の就職活動にも影響が出ています。
CBホールディングスが来年卒業予定の薬学生を対象に行ったアンケートでは、イベントの中止、延期などで90%が新型コロナの「影響があった」と回答しています。
しかし、病院や薬局では現場を見ておきたいという考えも強く、76%の学生が現場での説明会を希望しています。
希望の就職先は「調剤薬局」が最も多く54%、「病院」が31%となっています。また、現時点で内庭をもらっている学生も、46%いるとのことです。
日経メディカル 2020/4
コメント
3月には新型コロナの影響で内定取り消しに、というニュースも聞かれていましたが、早くも来年の採用についても影響が出てきているようです。
特に影響が大きいのは、合同説明会でしょうか。人が集まるイベントは軒並み中止となっていますので、例年であればこの時期に行われる合同説明会も同様に、中止となっています。
また、そうでなくても個別の説明会や面接は都市部で行われる事が多く、首都圏などで緊急事態宣言が出された今は、そういった活動自体がなかなか進まない状況になっていると予想されます。
面接などのスケジュールを先延ばしにしている企業も多いようですが、新型コロナの終息が見えない中いつまで先延ばしにするのか、判断に困るところかと思います。
ただ、安心材料として、調剤薬局やドラッグストアは新型コロナの影響は受けているものの営業自粛・停止となるような業種ではないという点があります。
調剤薬局も今は一時的にですが患者数が減っています。実際に私が勤務する会社では、店舗に寄りますが前年比1~4割程患者数が減っています。
しかし、新型コロナの影響が落ち着けばまた元に戻るため、その影響で採用を絞るということは考えにくく、来年の採用人数もそう大きくは変わらないでしょう。
医療業界はもともと不景気に強い業界と言われていますので、今回の件でもその点においては他の業界よりも安心できると思います。
どちらかというと、影響があるのは製薬会社でしょうか。特にMRは採用人数が減らされる可能性があると考えています。
現在、MRは病院への訪問を自粛されています。(日経新聞|日薬連、MRの医療機関訪問を自粛要請)
多くの医師は、これまでMRに頼っていた情報収集を、自らウェブなどを活用して行うことになっています。
もしも今の「MRがいない」という状況が続き、それでも医療現場には大きな混乱がなかったということになれば、かねてより言われていた「MR不要論」が加速していく可能性はあります。
私もMR経験者ですので、MRの必要性については理解しているつもりですが、今回の新型コロナをきっかけに、営業職が見直されるようになるのではと考えています。
来年から未曾有の不況に陥るのではと言われている中で、更に将来性も見据えて適切な就職活動をしたいところですね。
新型肺炎で研究開発停滞~臨床試験の遅延や中止相次ぐ
ニュース概要
製薬企業の「研究開発」にも大きな影響が出ています。
薬事日報社が製薬企業を対象にしたアンケートによると、回答企業の3分の1で臨床試験の遅延や中止といった状況になっているようです。
医療機関では新型コロナの感染拡大を防ぐため、治験の受け入れ拒否や臨床開発モニターの訪問規制をするケースが増えており、日本だけでなく、海外も含めたプロジェクトの見直しが求められています。
現段階での業績への影響は「調査中」とする企業が多いですが、影響が出る企業は多くありそうです。
薬読 2020/4/10
コメント
前の記事で就職イベントの中止について取り上げましたが、中止になっているのはイベントだけではありません。新型コロナの影響は、製薬会社の研究開発にも及んでいるそうです。
一番影響を受けているのは、記事にも挙げられている治験の段階です。感染リスクもあるため、医療機関もできるだけ治験の受け入れはしたくないというのが本音でしょう。
研究開発に関しては、武田薬品のように新型コロナの治療薬を研究している企業も多くありますので、それも他の薬の研究開発に影響を与えているのではと思います。
製薬会社は、他の業界と比べて特殊な面があります。その一つは、営業利益率と研究開発費が高いという点です。製薬大手の営業利益率は10~20%と軒並み高く、それと同時に売上高に対する研究開発費も10~20%と他の業界と比べても高くなっています。
つまり、製薬は一つの薬ができるまでに莫大な費用がかかりますが、一つ売れる薬が開発できれば、特許が切れるまでは高い利益率を保つことができるという企業体質になっているのです。
それだけ、製薬会社にとって研究開発は大きなウェイトを占める業務ということができます。
研究開発が滞ると、目先の利益ではなく、将来的な利益が失われることになります。現在各社が新型コロナの対応に迫られていますが、どのタイミングで研究開発を再開させるのかなど、対応を間違えると業界内での競争力を失ってしまう危険性があると思います。
また、研究開発だけでなく製造に関しても影響が出始めています。最近では海外での工場停止や輸出規制などによって、原料の不足などから流通が滞ってしまった薬も出てきています。
現場としては、今のところはそういった薬に対しては同成分の他メーカーの薬で対応していますが、今の状況が今後も続くようであれば、流通している薬が一層限られた状況になることが考えられます。
今、最も必要とされるのは新型コロナの治療薬でありますが、当然、他の疾患で新薬を心待ちにしている人は大勢います。早く今の状況が落ち着き、通常の研究ができる態勢に戻ればいいなと思います。
まとめ
いかがでしたか。今回は、「オンライン診療」「就職活動」「研究開発」という3つの観点から、今後業界がどう変わっていくのかを考えてみました。
特にオンライン診療に関しては政府の対策の目玉の一つとして、大きな話題となりました。調剤薬局で働いている人にとっては、遅かれ早かれ対応する必要のあるツールです。
今はまだ自社では対応していない人も、何もせず放っておくのではなく、いつ自分の職場で始まってもいいように、今のうちからポイントを押さえておきたいところですね。
新型コロナウイルスの感染拡大が続くと、仕事面でもどうしても不安に感じてしまいがちです。しかし、見方を変えれば、職場の利益が下がったときに「どうすれば業績を回復できるか」といったことをこれまで以上に真剣に考える機会が増えた、とも言えます。
今までになかった新しいものを考え付くチャンスだとポジティブに考えて、今の大変な時期を乗り越えていけたらと思います。
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。