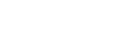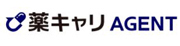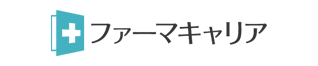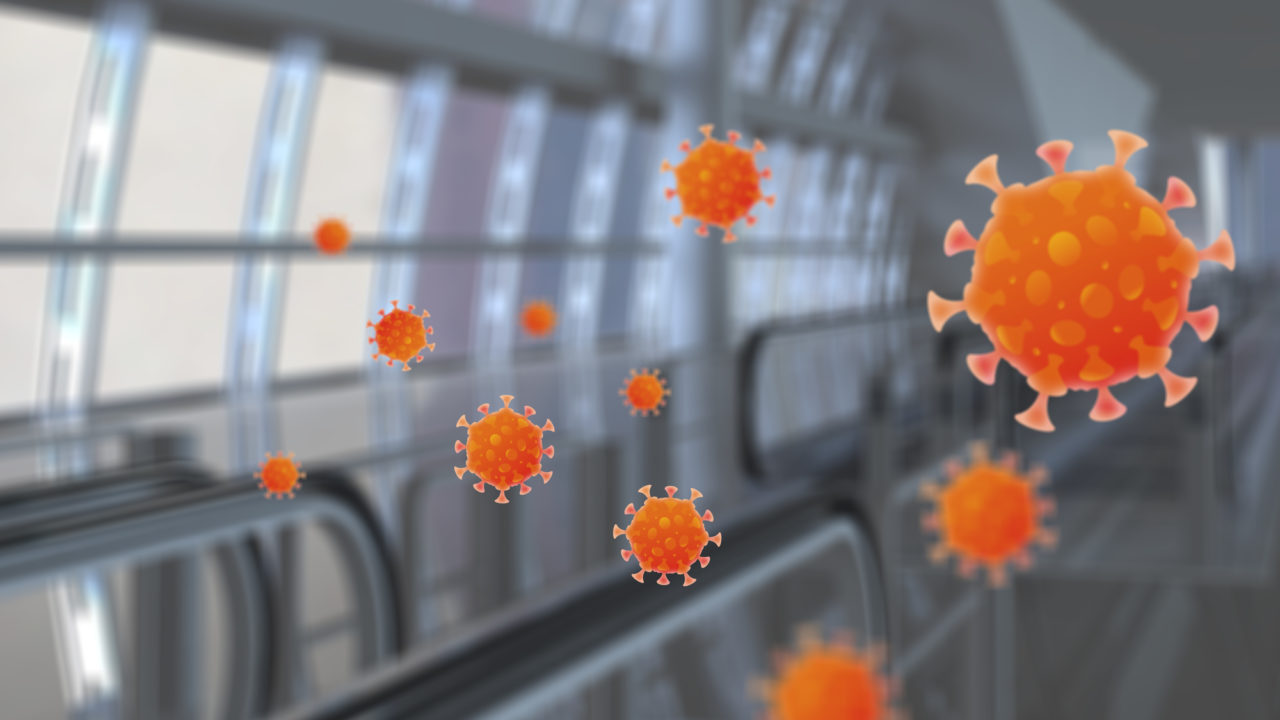
※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
こんにちは、けちゃおです。
今年はインフルエンザが昨年より流行せず、調剤薬局に来局する患者さんも例年より少なくなりました。「去年よりも忙しくないな」と感じた薬剤師の方も多いのではないでしょうか。
特に今年はコロナウイルスばかりニュースで取り上げられることもあり、「インフルエンザ」というワードをあまり耳にしない年でしたね。
さて、今月も薬剤師という立場で気になったニュースを3つ取り上げて解説していきたいと思います!
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
この記事の目次
「手作り目薬」炎上ブログ記事削除 運営のサンケイリビング新聞社が「誤った内容あった」と謝罪
ニュース概要
子育てサイト「あんふぁんweb」に掲載された記事に誤りがあったとして、運営元が記事を削除、謝罪する事態がありました。問題となったのは、手作りの目薬を紹介する記事です。
衛生面や、「塩は塩化ナトリウムが入っていないものを選ぶ」といった間違った情報が記載されていて、SNSを中心に炎上していました。
運営元のサンケイリビング新聞社は、記事の監視体制の強化などで再発防止に努めるとしています。
Yahooニュース 2020/2/10
コメント
webサイトに間違った医療情報が掲載されていたという今回の問題。こういった問題はたびたび耳にしますが、医療従事者としては、ありえない内容だと思います。(医療従事者でなくてもおかしいと思うでしょうが)。
今回問題となっているのは、自宅で手軽に目薬が作れるという内容です。まず、はっきりさせておきたいのは目薬もれっきとした薬であるということです。
医療用の目薬の場合、製造段階から衛生面にはかなり気を使っていますし、使用する際も「開封後は1ヶ月が期限の目安」とされています。
なので、目薬に限らず自宅の環境で「薬を作る」ということもありえないですし、そもそも薬と呼べるものではありません。ましてや、生理食塩水ということで、一体どんな効果を期待していたのでしょうか。
今回の問題で思い出されるのは、2016年のWELQの問題。このときは、医療の資格がない素人が書いた医療系の記事が大量に検索上位を占めるという事態になり、ネット上の医療情報の取り扱いが変わるきっかけとなりました。
最終的にはこのサイトが閉じられることになっています。この時は、医療系の記事でありながら専門家のチェック等がされていないということが大きな問題点でした。
それ以降、医療に関する情報にはどのサイトも厳しくなったと思っていますが、今回のケースも、恐らく医療従事者による監修などはされていなかったのでしょう。医療系のサイトではなく、子育て情報サイトなのでこんな問題が起こるとは考えていなかったのでしょうか。
私は、薬剤師をやりながらウェブライターをしています。もちろん、医療系の記事について依頼を受けることは多々あります。
「自分が書いた記事で人の健康に役立つ」というのはやりがいもありますが、その反面「間違った情報を流せば、不特定多数の人の健康に被害が及んでしまう」という危険性もあります。
そのため、医療系の記事を執筆する際には、自分の記憶だけで書くのではなく、文献等をしっかり調べて間違いのない情報を届けるようにしています。また、チェック体制が整っていないサイトに関してはできる限り依頼を受けないようにしています。
今回の問題を受けて、今後はもっと規制が厳しくなることも予想されます。個人的に危惧しているのは、信頼できる情報を届けている良質な情報サイトまで信頼されなくなってしまう可能性があることです。
私も執筆にあたりさまざまなサイトを参考にしていますが、当然信頼性が高いサイトも沢山あります。しかし、専門知識のない人にとっては、それが正しい情報なのか、間違った情報なのかを判断するのが非常に難しいものです。
正しい情報なのかを判断するために、医療情報の記事を読む際には、その執筆者がどんな人なのか、その情報の根拠はしっかりしているのかを調べることが大切です。
医療従事者が書いているのであればある程度信頼性は高まりますし、情報元が厚生労働省や製薬企業などであれば安心できますよね。今後は薬剤師を含めた医療従事者が執筆、監修をした記事の価値が上がっていくものと思われます。
ロボット、遠隔医療…新型コロナウイルスとの“戦争”を背景に、中国のIT技術がさらに進化か
ニュース概要
中国ではコロナウイルスの感染が問題となっていますが、その中でドローンが物資を運ぶ様子が話題となるなど、IT技術が進んでいるさまも見て取れるようになっています。
戦争が起こると科学技術が飛躍的に進化すると言われていますが、今回のコロナウイルスに関しても同様の進化がみられるのではと考えられます。
ドローン以外にも、5Gを使った遠隔診療や病院での看護ロボットなどが積極的に取り入れられるようになってきています。
Yahooニュース 2020/2/10
コメント
コロナウイルスの話題は連日騒がれていますが、今回はその中からひとつ、中国のIT技術の革新とのつながりについて考えてみたいと思います。
今回の記事では、ドローンによる物資の配送や病院でのロボット活用、オンライン診療などが紹介されています。どれもこれからの技術として話題になることは多いですが、まだ広範囲での実用化には至っていない分野です。
もともと、中国は日本と比べてもこういった技術への取り組みは早いと感じていました。日本では例えばドローンを飛ばすのにも法整備に時間がかかり、商業用ドローンの実用化が他国よりも遅れています。その点、中国ではそういった規制が日本よりは厳しくはないので、いち早く実用化することができるのです。
そして、今回のコロナウイルスの流行という出来事によって、その技術はさらに進歩するのではと思います。人から人へ感染するウイルスであるため、それを避けるためにドローンやロボット等が使われるようになるからです。
この行動力の速さという点においては、日本も見習わなければならないところだと思います。実際、今後日本でも同様の流行が起きたとして、同様の素早い対応ができるとは思えません。
コロナウイルスの流行自体は大きな問題ですが、それが収束した時には日本よりも数歩進んだ技術も持つことになるのではと思います。
重複投薬 解消促す 特許切れ薬 値下げ早く
ニュース概要
今年の診療報酬改定では、薬剤師の業務に対する報酬が一部見直されます。
その一つが、重複投与の解消に取り組んだ場合の加算です。複数の医療機関を受診していて、同じ効果の薬が処方されていた場合、6種類以上の薬を処方されていた患者であれば解消を提案することで報酬に1000円を上乗せすることができます。
他の改定も含め、今回の改定には門前薬局ではなく、患者一人一人に丁寧に対応するかかりつけ薬局を増やす狙いがあります。
日経新聞 2020/2/8
コメント
今年は、診療報酬の改定があります。毎回のことではありますが、今回も全体的には薬局にとって厳しい改定となっています。これまでよりも多くの店舗で調剤報酬の減額が行われるので、利益が半減する見通しのところも多いのではないでしょうか。
そんな中で、加算項目として挙げられているのが今回の記事にもある、重複投与是正の加算です。他の病院とで重複した内容の薬があった場合、医師に連絡して重複している薬を減らしてもらうと加算できるものです。
最近は、特に「医薬品のムダ」について問題視されることが増えてきています。前回は患者さんの残薬解消についての取り組みをご紹介しましたが、それと同じくらい重複投与の解消というのは薬剤師の業務としても大事なところです。
実際に、気付かず重複投与となっている患者さんもいるかとも思いますし、病院に伝えていなくても薬局でのヒアリングで重複投与がわかるケースは、よく見かけます。
ただ、この加算には「6種類以上の薬を処方されている」などの条件があり、すべての患者さんに対して提案できるのではないということは注意が必要です。
一方で、薬局としては、積極的に取り組むほどのうまみがないという点もあります。今回の改定では、医療機関に重複投与改善の提案をしたら100点、となっています。
もちろん処方単価としては高くなりますが、例えばかかりつけ薬剤師加算は一度同意を貰えばその後来局のたびに加算が取れるのに対し、この加算は一度きりの加算です。
継続性がないため、薬局の利益としてはあまり魅力的な加算ではありません。それなりに手間と時間もかかることから、必要以上のヒアリングをしない、あまり積極的に取り組まない薬局も多いのではないかと思います。
ただ、もちろん重複投与の薬を減らすことは患者さん健康のため、金銭的な負担を減らすためにもなりますし、国の医療費削減にも関わるところです。
国が最終的に求めているのは、「複数の医療機関からの薬も把握できる、かかりつけ薬剤師としての機能」なのだと思います。患者さんのかかりつけとなって、服用している全ての薬を把握、管理する。その中で残薬や重複投与があればなくすように行動していく、ということが大切なのだと思います。
重複投与をなくすためには、患者さんとのコミュニケーションが必要ですし、円滑に行うためには病院との関係性が良好であることも大切です。コミュニケーションスキルは苦手とする薬剤師も多いですが、今後必ず必要となってくるスキルですので、意識的に高めていきたいところですね。
まとめ
今回は、
- webメディアでの医療情報の取扱いについて
- 中国のIT技術の革新とコロナウイルスの関係
- 重複投薬のメリット、デメリット
の3点についてお話ししました。特に、1つ目のあんふぁんwebの問題は、改めてwebメディアのあり方について考えさせられました。私自身、薬剤師という傍から見れば「専門家で信頼できる」とみられる立場ですので、発信する情報には相応の責任をもって発信しなければならないと改めて感じました。
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。