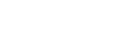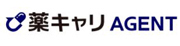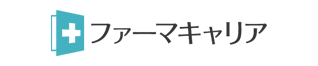※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
こんにちは、けちゃおです。年も変わり、2020年になりましたね。2019年も多くのニュースについて解説をさせていただきました。
今回は、2019年の1年間で私が特に医療・薬局業界に影響を与えたと思ったニュースについて、3つピックアップしてみました。
そこから業界が今後どうなっていくのか、どうなっていくべきなのかを考えてみたいと思います。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
調剤薬局大手が医薬品のSPAに見出す活路
ニュース概要
調剤薬局業界で、製薬に力を入れる企業が増えてきています。
国内2位の日本調剤は製薬の大型工場の稼働が始まり、3位のクオールホールディングスも参入を表明しました。
その裏にあるのは調剤薬局の収益悪化です。薬局の収入の柱の一つは調剤報酬ですが、診療報酬の改定によって特に大手調剤は大きな打撃を受けています。
またもう一つの柱である薬価差益に関しても、薬価の引き下げが続いている現状で今後の大幅な上昇は見込めません。利益率を改善させるため、自ら薬を作り、売るというビジネスモデルに活路を見出そうとしています。
日経新聞 2019/12/25
コメント
1つ目に、大手調剤薬局による製薬部門の立ち上げというニュースを取り上げさせていただきます。
なぜこの話題を取り上げたかというと、今後調剤薬局業界がとうなっていくべきか、そのあり方について考えることができると思ったからです。
2019年は、調剤薬局にとっては大きな変化が感じられる1年だったと思います。その影響のひとつといえるのが、2年に一度行われる診療報酬改定です。
2018年度の改定では、特にチェーン薬局にとって調剤基本料が減点となる店舗が増えるなど、店舗によっては利益を大きく落とす結果となりました。
また、「かかりつけ薬剤師指導料」が引き上げられ、「地域支援体制加算」が新設されるなど、これまでの業務に加えてプラスアルファで何に取り組んだか、が重要視されるようになってきています。
2020年の診療報酬改定についても方向性が示されていますが、技術料の引き下げやかかりつけ機能の強化といった面は今回も盛り込まれると予想されています。
これまでも改定の度に影響を受けてきた調剤薬局ですが、近年は特に厳しい改定になっていると実感している人も多いのではないでしょうか。そのような状況で生き残るため、今の薬局業界には2つの大きな流れがあります。
その一つは、大手調剤薬局による中小・個人薬局のM&Aです。個人薬局では経営が立ち行かなくなることを予想して、大手の傘下に入るという業界再編の流れは今後も加速していくと思われます。
そして、もう一つは調剤分野以外にも参入して事業の多角化を図るというケースが増えてきていることです。
本業である調剤部門は今後も利益が縮小していくことが予想されますが、それでも現段階では安定して利益が見込める事業であることに変わりありません。本業で十分な利益を確保できている間に、他の分野で柱となる事業を確立させたいという思惑があるのだと思います。
多角化の内容に関しては企業それぞれの方針がありますが、その中の一つが、今回の記事にある「製薬」というジャンルです。
自社工場で医薬品を作って自社の薬局で調剤する、という流れが一本化できれば、大幅な利益率アップが期待できます。
ただ、いくら薬に携わっているからとはいえ、製薬というのは調剤薬局にとっては経験のない分野です。例えば他のメーカーのような創薬技術で薬を作ることができるのか、といったことは未知数だと思います。
今後も大手調剤を中心に製薬に参入する企業が出てくる可能性はありますが、莫大な設備投資費がかかる上に、流通経路の確保などはどこまでできるかわかりません。製薬~薬局での投薬までの流れを安定させるには大きな時間とリスクがあると思います。
なので、今回の記事にある日本調剤、クオールにはそのパイオニアとして期待しています。この大手2社がどれだけこの事業を成長させることができるかで今後の他社の動向も変わってくるのではないでしょうか。
将来は、素の薬局で出ている薬を全て自社でまかなう「自給自足」の薬局も出てくるかもしれませんね。
人口知能(AI)の利用で早期のがん発見を実現
ニュース概要
がんは日本人の2人に1人がかかる病気です。治療法も進化して、今では早期発見すれば大幅に生存率を高めることができます。
早期発見のために、人工知能(AI)を利用して各部位のがんを早期に診断する方法にスタートアップ企業が取り組んでいます。
開発においては多くの病院と連携して、数多くの診断画像を読み込ませて制度を向上させてきました。
今後は大手企業とも連携を取りながら、早期の一般へのサービス提供を目指しています。がんの早期発見は万国共通で、技術が確立されれば世界中での利用が期待されています。
日経新聞 2019/12/13
コメント
2019年によく耳にした言葉に「AI」があります。
私が昨年ピックアップした記事の中にもAIに関する記事はいくつかありましたし、実際にAI技術は医療の分野でも大きく前進した年だったと言えます。
今回の記事にあるように、多くのスタートアップ企業ががんの診断などにAI技術を取り入れています。過去のデータを蓄積させ、適切な診断を行うというのはAIが特に得意とするところですので、2020年以降も更なる技術向上が見られるのではと思います。
がんに関しては、2020年に10万人を対象とした全ゲノム解析が行われる予定もあり、がんの病理解明や治療に役立つのではと期待されています。
将来的には、AI診断で早期発見をして、ゲノム解析をもとに治療を行うという、これまでとは全く異なるアプローチでがんの診断、治療を行うようになっていくと思います。
まだ全く想像できない未来ではありますが、近年のAI技術の革新を見ていると、そう遠くない未来なのかなとも感じています。
また、AIが活用されるのは診断だけではありません。既存薬の別の効能をAIが予測したり (日経新聞|2019/10/19)、 工場の検査工程にAIを導入 (日経新聞|2019/11/27)、 AIで創薬を効率化させる (日経新聞|2019/11/1)など大手製薬企業が様々な使い方を見せています。
AIはまだ技術としては始まったばかりで、ここにあげた活用法についても実際にどの程度の費用対効果があるのかは分かりませんが、今後はどの分野でもAIをいち早く導入した企業が生き残っていく時代になるのではないでしょうか。
AIが活躍の場を広げることで、期待されるのは業務の効率化や人件費削減です。
高齢化社会が進み、働く世代が減ってきていますので、今後はAIに任せるところは積極的に任せていくべきだと思います。
ただ、AIでの業務が広まることで、企業のリストラにつながるのではないかとの心配もあります。
また、利用者側としては、広く一般的に使われるようになるのはいつなのか、また費用はどの程度かかるのか、といったことが気になるところです。
仮に安価で診断を受けられるような時代になれば、AIによるがん診断というのは一つのスタンダードになりそうですね。
雇用年齢の長期化がもたらす経済効果と転職市場に与える影響
ニュース概要
政府は高齢者雇用安定法の改定案を発表しました。これまでの65歳から、70歳まで働くことができるよう、企業の選択肢として7項目を設けています。70歳まで働くことで、経済効果も期待されます。
調査では65~69歳の高齢者で就業を希望しているのは65%ですが、実際に働いているのは46.6%にとどまっています。
希望する高齢者が意欲的に働くことができ、企業の負担も軽減できるように自社での雇用以外も選択肢にいれた努力義務としていますが、将来的には義務化される可能性もあります。
日経新聞 2019/5/15
コメント
医療関係のニュースではありませんが、薬剤師も含めて今後の働き方について考えさせられるものでしたのでピックアップしました。
現行の高年齢者雇用安定法では、65歳が定年と決められていました。当然、皆さんの将来設計としても「長く働いたとしても65歳まで」という認識があったのではないでしょうか。
しかし、今後は70歳までの雇用の努力義務が企業に課されることになったのです。もちろん、これは強制ではなく、あくまで「働きたいと希望する人には」働ける環境を整えるというだけです。
ただ、今後は65歳を超えた高齢者であっても働かなければならない人が増加することが予想されるのです。
その理由のひとつは、年金制度の改正です。現在検討が進められている年金制度の改正案は、年金の受給開始年齢を75歳まで選択できるようになっています。
原則の65歳から受け取ることもできますが、受給開始を遅らせることで月々のもらえる年金額が大幅にアップするというしくみです。
そのため、65歳を超えても元気なうちは働いて、70歳や75歳になってから年金を受け取るという選択をする人も増えてくることが考えられます。
それはどの職業にもいえることで、薬剤師でも例外ではありません。
薬剤師の場合は、高齢になっても資格があるので、いつまでも薬剤師として働く事が可能です。時短であってもある程度の時給は保証されているので、65歳を過ぎても働き続けるということは他の職業よりも無理せずできるような気がします。
そうなったときに、もう一つ変化がありそうなのは転職市場です。今までは、転職をするなら30代まで、というのが転職市場の常識でした。
しかし、今後は40~50代のこれまでは積極的な転職をしてこなかった年代も、この先長く働くことができる環境を求めて転職をするということが増えるのではないかと思います。例えば高齢でフルタイムで働くのが難しくなってもそのまま働かせてもらえる職場などがあるといいですよね。
ただ問題は、今後更に高齢化が進んでいきますので、働く高齢者の数は増えていくが、その一方で受け皿が減っていくのではないかということです。調剤薬局の数は今が頭打ちといわれていて、調剤薬局やドラッグストアが将来的にどの程度高齢者の雇用を確保できるのかは未知数なところがあります。
また、あまりに高齢者の雇用が増えすぎてしまうと、それが若い世代の雇用を奪ってしまうことにならないかという懸念もあります。
例えば、調剤薬局の役員をしている薬剤師が60代になっても辞めずに居座っていたら、なかなか薬剤師の若返りができませんし、役員報酬をそのまま受け取っていたらその分コストもかかることになってしまいます。
若い世代を優先しつつ、高齢者にとっても働きやすい環境になってくれたらと思います。
まとめ
いかがでしたか。たった1年間でも、業界は大きく変わったなと改めて感じました。
最後の記事で高齢者の雇用について述べていますが、私がその年代になるころには高齢者を取り巻く環境も大きく変わっているんだろうなとも思います。
日々変わっているからこそ、時代に取り残されないように常に業界の動きにアンテナを張っておくことは大切だと思います。
今年も、ニュースを紹介することで皆さんのお役に少しでも立てたらと思います。よろしくお願いします。
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。