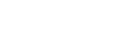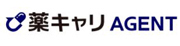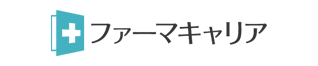※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
12月に入り医療の現場も忙しさを増してきています。
毎年この時期になると気になるインフルエンザの流行ですが、今年は流行が早く、年末年始がピークになるとも言われていますので、旅行や帰省をされる方は気を付けたいところですね。
今回も、12月の薬に関するニュースを3点ピックアップして、現場目線での意見をお伝えしていきます。薬剤師としてできることは何があるか、考えるきっかけになると思いますので、ぜひ読んでみてください。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
不妊治療、スマホで再診 アプリ「ルナルナ」と連動
ニュース概要
医療関連サービスのカラダメディカが、不妊治療のオンライン診療システムを開発しました。親会社が女性の妊活をサポートするスマホアプリ「ルナルナ」を運営しており、それと連動してサービスを提供します。
具体的には、ルナルナの画面からオンライン診療のための医療機関検索が行えるようになり、受診の予約からビデオチャットでの診察、処方箋の受け取りまで行えるようになります。
カラダメディカは「不妊治療とオンライン診療は相性が良い」と考えており、今後は電子カルテとの連携なども視野に展開していくとのことです。
日経新聞 2019/12/7
コメント
インターネット診療に関するニュースはこのコーナーでもたびたび取り上げていますが、今回は不妊治療に関するものです。
私も不妊科の門前薬局で働いた経験がありますが、不妊治療で来られる患者さんは、他の診療科にかかっている患者さんとは明らかに異なる点が2つあると思います。1つは「病気で受診しているのではない」ということ、そしてもう一つは「周囲に知られたくない」ということです。
もちろん、病気で病院にかかっている患者さんも「周りに知られたくない」と感じることはあるでしょうが、不妊治療の患者さんはそれが顕著です。
そのため、服薬指導の際も「他の人から見えないように仕切りを作って欲しい」「薬の名前は言わないで欲しい」などと要望されることが多々あります。
また、病院は産婦人科や小児科も併設していることが多く、妊娠中や子連れの患者さんと薬局内で一緒になることもありますので、特に気を遣って対応しています。
また、不妊治療は保険適用外となることが多く、金銭面で大きな負担となります。
そのため、本ニュースでも触れられているように仕事をしながら不妊治療を行う人も多く、そのような人は仕事が終わった夜遅い時間に受診することになります。
仕事と不妊治療を続けていかなければならない、ということで体力面、心理面でも負担が大きいものです。
このような現状から、不妊治療を行いたいけれど病院、薬局に行きたくない、または行く時間がないと考えて治療を継続出来ない患者さんは少なからずいるように思います。
今回のニュースにあるスマホアプリとの連動によるオンライン診療は、こういった不妊治療への抵抗感をなくすのに有効なツールになると思います。
残念ながら薬局に関しては触れられていませんでしたが、今後診察だけでなく薬局による服薬指導に関してもオンラインでできるようになれば、不妊治療のハードルもより一層低くなり、今まで以上に気軽に不妊治療を始められるようになるのではないでしょうか。
不妊治療を始める人が増えると、当然期待されるのは出生率の改善です。近年は特に晩婚化が進み、不妊治療の必要がある夫婦の割合が増えています。
私は30半ばですが、同年代の友人の中には「30歳を過ぎて結婚して、不妊と診断されたが、治療をしてまで子どもをほしいと思わない」と考えて子なしを選択している夫婦もいます。
不妊治療のマイナスイメージが薄れれば、このような夫婦の考えを変えるきっかけになるかもしれません。
ただ一方で、調査によるとオンライン診療の普及は進んでいないという現状があります (詳しくはこちら)。
オンライン診療という言葉自体にまだ馴染みがなく、始めるにはハードルが高いと思われているようです。
新しく始まるシステムということでここ数年でオンライン診療に参画する企業が増え、システム上は問題なく運営できるようになっていると思います。
しかし、そこに法整備や普及活動が追い付いていない印象です。
今回のような一企業だけの活動では普及にも限界がありますので、国がもう少し関与して、広くオンライン診療や、不妊治療を広げるための施策を打ってほしいと思います。
薬剤耐性菌で年8000人死亡 国内で初推計、影響深刻
ニュース概要
国立国際医療研究センター病院などの研究チームは、2017年に抗生物質の効かない「薬剤耐性菌」で亡くなった人が8千人にのぼるとの統計をまとめました。
今回は日本で検出の多いMRSAとフルオロキノロン耐性大腸菌という2種類のみを調べたものですが、耐性菌の死者数を全国規模で調べたのは初めてです。
海外でも耐性菌による死者の増加が指摘されていますが、日本でも大きな影響が出ていることが明らかとなりました。
今後は、抗菌薬の適正使用に関して今まで以上に厳しい対策が求められます。
日経新聞 2019/12/5
コメント
薬剤耐性菌のニュースも、最近取り上げられることが増えてきています。今回指摘されている情報としては、薬局で働く身としては今更感もありますが、それだけ世間の認識では「風邪=抗生剤」と考えてしまう人も多いのだと思います。
かねてから、抗生剤の効かないウイルス性の風邪などに対する抗生剤の処方については問題とされてきました。
ウイルスが原因の場合、抗生剤が効かないだけでなく、不必要な抗生剤の服用を続けることで抗生剤の効かない「耐性菌」を発生させる結果となるからです。
今回、抗生剤に関する国内死者数として初めて具体的な数字が上げられたことで、改めてその怖さを実感することとなりました。
耐性菌は抗生剤を適切に服用していればある程度防げるものでありますので、その適正使用を伝えていくのが薬剤師を含む医療従事者の役目であると思います。
今回、耐性菌による死者は年間8,000人程度という結果でした。今回調査されたのはMRSAとフルオロキノロン耐性大腸菌という2つの菌に関してだけでしたので、他の菌も考えれば1万人は超えると見られています。
これがどの程度多いのか、他の疾患と比較してみるとわかりやすいと思います。
毎年冬場に猛威をふるうインフルエンザでは、年間1万人程度が死亡すると言われています。あれだけ騒がれるインフルエンザに匹敵する人数が、人知れず耐性菌で亡くなっていることになります。
耐性菌は国際的な問題で、日本でも様々な対策が取られています。
実際、徐々に不要な抗生剤の処方は減ってきています。しかし、まだ患者側の認識も浸透していませんし、より抜本的な改革が必要になるのではないかと思います。
その1つとして考えられるのは、診療報酬です。2018年度の診療報酬改定で、乳幼児に対して風邪などの症状で抗生剤が不要と判断した場合、病院側に報酬が支払われる「小児抗菌薬適正使用加算」という仕組みが始まりました。
確かにこれにより抗生剤の処方を控える病院は増えると思いますが、私はこの仕組も、「適正な使用をしたら加算する」のではなく、「適正な使用ができないのなら減点する」ことが正しいと思います。
例えば、不必要な抗生剤の処方と判断された場合は病院側の点数を大きく減点する。そうすることで、病院側もより抗生剤の処方に関して意識的になるのではないでしょうか。
残念ながら、薬剤師としてできることは医師ほど多くはありません。なぜなら、医師が不必要に抗生剤を処方したとしても薬剤師が変える権限はないからです。
明らかに間違った処方であれば疑義照会をして、処方を変えてもらうことはできますが、普通の風邪で抗生剤が出たとしても病院に疑義照会することはありません。
また、薬剤師の独断で「今回の抗生剤は飲まなくてもいいですよ」などと指導することも駄目です。抗生剤の適正使用のためには、医師の意識改革が必要不可欠なのです。
かといって、薬剤師にできることはゼロではありません。一つ、私の知り合いの薬剤師の例をお話しします。
その方は、管理薬剤師として調剤薬局で働いていますが、門前の病院は各メーカーとのつながりも強く、抗生剤を頻繁に処方する病院でした。
しかし、医師との面会を重ね、抗生剤の適正使用を訴えた結果、不必要と判断した場合には抗生剤を処方しないという考えに変えることができました。
薬を処方しないという選択はメーカーや病院、薬局にとっては利益が減ってしまうことになりますが、患者さんの健康に直結することですので、「処方をしない」という選択をする病院が増えてくれることを期待しています。
高齢者にリスク高い薬、80代処方ピーク 睡眠・抗不安
ニュース概要
厚労省のデータによると、高齢者に対して睡眠薬や抗不安薬が多く処方されている実態が明らかになりました。
高齢者は服用によって転倒や認知機能障害が起こりやすくなるという研究も数多くあり、依存性や死亡リスクも上昇することが報告されています。しかし、これらの薬は65歳以上に53%と多く処方されています。75歳以上で見ても33%に上り、ピークは80代でした。
高齢になると排泄機能も低下し、薬が効きすぎてしまったり、副作用が強く出てしまう危険性があります。高齢者への睡眠薬、抗不安薬の処方に関しては、慎重に扱うことが提言されています。
朝日新聞 2019/12/7
コメント
高齢者の睡眠に関するニュースです。睡眠薬や抗不安薬は高齢者に多く処方される傾向があるようです。
若い人の方が仕事などのストレスで不眠になることが多いように思っていましたので、高齢者の方が多く処方されていることは意外にも思えます。
ただ、確かに睡眠薬は高齢者に対して特に多く出ているように思います。というより、高齢者の場合は他の薬をもらうついでに睡眠薬をもらう事が多いので、結果として処方が増えている、ということだと思います。
若い世代では他に薬をもらっていない人も多いので、わざわざ睡眠薬だけのために受診することも少ないですし、不眠などがあっても体力もあるので多少無理してしまうこともありますよね。
今回の記事では、高齢者の過度な睡眠薬、抗不安薬服用によるリスクが紹介されています。
もちろん依存性も高まりますので、飲まずに生活できるのが望ましいのですが、そもそも高齢になるにつれ平均睡眠時間は徐々に短くなると言われています。
また、特に男性では前立腺肥大による夜間頻尿などで寝れないことも多く、生活の質を守るためにはある程度の服用は仕方ないのかなとも思います。
実際、高齢の睡眠薬服用患者に服薬指導をしていると「薬に頼りたくはないけれど、飲まないと寝れない。」という悩みをよく聞きます。
そのような状況では薬剤師としてアドバイスできることは少ないですが、生活習慣の見直し、特に早寝や早朝のウォーキングなどを避け生活リズムが前倒しにならないようアドバイスすることは必要になるかと思います。
また、今回のデータは厚労省が過去のレセプトデータから集計して作られたものとのことです。最近はこういった統計を目にする機会が増えました。
年齢別、性別などでまとめることで、処方の傾向がわかりますし、今回のような処方の問題点や医療費削減のヒントにつながることもあると思います。
データは作成して終わりではありません。そこから得られた問題点を、しっかり解決するように動いてほしいと思います。
まとめ
今回は、
- 不妊治療
- 抗生剤(耐性菌)
- 高齢者の睡眠薬、抗不安薬
という3つのジャンルにスポットを当てて解説をしてきました。
どれも薬剤師をしていれば対応することのある薬ですが、正しく服用してもらうための対応の難しさは日々感じるところです。
一個人としてできることは微力ではありますが、抗生剤の適正使用など、目の前の患者さんに正しい情報を伝えていくことは大切ですので、高い意識を持って日々の業務に取り組めるといいですね。
HOP!ナビとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。